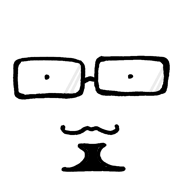「cakes(ケイクス)」に見る新しい読み物の形

先日、博多華丸・大吉の博多大吉さんのラジオ「たまむすび」のPodcastを聞いていた時、大吉さんが今度cakes(ケイクス)に読み物を出すと言うコトを話されていて、ん?cakes(ケイクス)って?何?となり遅ればせながら初めてcakesの存在を知りました。
cakes(ケイクス)って何?
ご存じない方にcakesのコトをご紹介しますと、「もしドラ」でおなじみの「もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの「マネジメント」を読んだら」や「スタバではグランデを買え!」など多くのヒット作を編集者として手がけてきた加藤貞顕さんが当時勤めていたダイヤモンド社から独立し、今までにない新しいコンテンツサービスとして始めたのがこのcakesです。
cakes(ケイクス)は、デジタルコンテンツ配信プラットフォームです。
コンテンツとのまったくあたらしい出会いの場として、読者とクリエイターをより身近に結びつけ、ものづくりをもっと楽しくします。
とcakesでは紹介しています。
無料で読める記事も沢山あるので、まずはとっかかりとして無料の記事を読んでから気に入った記事や人がいたら有料会員(1週間に150円)になって読んでみるのがお勧めですね。
実際に記事を読んでみた
2014年2月5日現在、記事を書いているクリエーターは261名で、ホリエモンこと堀江貴文さんや株式会社ドワンゴ代表取締役会長でスタジオジブリのプロデューサー見習いとしても顔のある川上量生さん、株式会社サイバーエージェント代表取締役社長の藤田晋さんなどIT企業の起業家などの記事から、博多大吉さんやマキタスポーツさんなどお笑いの方がいたりサッカー選手の中村憲剛さんなどスポーツ選手がいたりと幅広い人物が記事を書いています。もちろん読ませるサイトなので作家の平野啓一郎さんや岩崎夏海さん、漫画家の山田玲司さんなどが掲載しています。

前都知事の猪瀬直樹さんがいたと思ったら今回都知事に立候補している家入一真さんまでいたりと掲載している人を見ているだけでも面白かったりします。
さて、今回の目的の人である博多大吉さんの記事はというと、

すでに3つの記事が掲載されていて、記事もテレビやPodcastなどで見る・聞く、いつもの悟った感もしくはおじいちゃん感出しまくり(良い意味です)の大吉先生の記事でした。
自然と読むことに集中できる構成
記事ページに飛ぶと基本的に文章と写真があるだけのある意味とてもアッサリとしたページ構成になっています。現在のネットの多くのコンテンツではバナー広告を載せるコトで収入を得ていますが、cakesでは潔い程に広告を載せていません。これについて加藤貞顕さんは
バナー広告のようなものを入れることはいまのところ考えていません。もし、企画としてやるんだったら、結果的に広告になっていた、というコンテンツとして面白いものとしてやりたいです。
エキレピより
とインタビューで答えています。
バナー広告を載せないことで他のコトに目を奪われずに記事に集中できます。更に一つの記事自体の分量が多すぎず少なすぎないちょうど良い長さなので、一つの記事を読んだら次のも読みたくなります。
記事を作るのにちゃんと編集者やカメラマンなどが関わっている
一つの記事を作るスタンスもしっかりとしていて、編集者やカメラマンが入り記事を作り上げていくのでクオリティも高くなっています。
一つの記事に対して人数をかけるコトが出来るのにはクリエーターに対するギャランティーの仕方による所が多い。
はい、やっぱりクリエイターさんには多めに還元したいなと思ってるんですよ。で、我々はメディアとして著者に原稿を依頼して、一から原稿を書いていただくこともあるんですが、その時は、著者の方には分配原資の60%の外側、つまり弊社分の40%の部分から最低保障の原稿料をお支払いします。クリック数によって決まるギャランティーの部分、これを我々はPVシェアと呼んでいるのですが、この金額が最初の原稿料分を超えたら、支払いがそちらに切り替わります。出版界の例で言いますと、翻訳書を刊行する際によく使われるアドバンス(印税前払い金)のような仕組みですね。
ビジネス+ITより
使うごとに自分仕様に記事構成がカスタマイズされていく
cakesが独自に開発したアルゴリズムで、自分が読んでいった記事内容が解析されるのでお勧めの記事が上位に表示されるようなるそうです。
キャッチフレーズに「クリエーターと読書をつなぐサイト」とあるようにcakesはあくまでプラットフォームという立場にたってサイトを運営していくそうで、この先どのように発展していくのはユーザーの使い方次第かもしれませんね。
まずcakesで試しに記事を書いて評判が良かったら書籍化するなんてコトもやっているので、本屋で立ち読みする感覚でcakesで記事を読むなんてコトもこれから普通になるのかもしれません。有料ブログなどと違う新しい形の読み物コンテンツサイトが流行るように有料会員になろうなかな。
2014/02/05